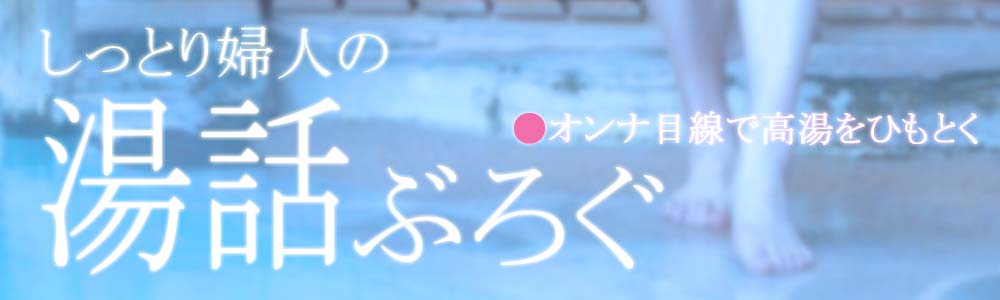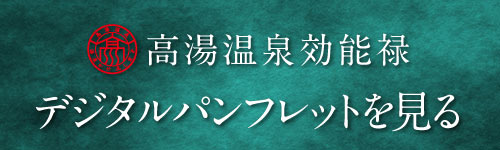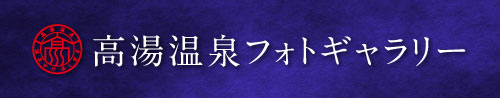- Takayu Hot-Spring Resort
- Arinomamano ONSEN
高湯温泉紀行
高湯温泉紀行
夏の浄土平湿原・吾妻小富士と静心山荘の寛ぎ
2018/07/某日
雲上の絶景、磐梯吾妻スカイライン
記録的な猛暑となった今夏。高湯温泉と土湯峠をつなぐ山岳観光道路、磐梯吾妻スカイラインの途中にある「浄土平」(標高1,600m)は、市街地より約10℃も涼しい人気の避暑スポット。ここは美しい景観で人気の「鎌沼」や「景場平」、「一切経山」、「五色沼(別名“魔女の瞳”)」等のトレッキングコースの起点としても知られている。「浄土平」には駐車場やレストハウスを囲むように「浄土平湿原」をはじめ「吾妻小富士」、「桶沼」といった1~2時間程度でまわれる見所も集中し、ドライブがてらの観光にもおすすめ。今回はこの「浄土平」の魅力についてあらためてご紹介したい。
ちなみに高湯温泉は、福島駅から国道70号線経由で約20km西に進んだ吾妻山の中腹、標高750mの高地にある。スカイラインの北の玄関口でもある高湯温泉は、「浄土平」観光の拠点にも便利だ。
“日本の道百選”にも選ばれた磐梯吾妻スカイラインの平均標高は1,350m。雄大な吾妻連峰を縫うように走る“空の道”は、全国のバイカーによる国内ベスト6のビューロードにも選ばれ、素晴らしい絶景が楽しめる。
そのひとつ「つばくろ谷」は必見の景勝スポット。深い峡谷に建つ高さ84mのアーチ橋からは山側に不動滝の姿が、谷側に折り重なる翠の山嶺と福島の市街地が遠望できる。「つばくろ谷」はスカイラインの中でも屈指の展望とあって、駐車場やトイレも完備。紅葉シーズンには平日も多くの観光客で賑わいを見せる(写真は紅葉時のもの)。ここに来たらぜひ、車を降りダイナミックなパノラマを楽しんでいただきたい。
そこから少し先、「天狗の庭」と呼ばれる見晴らしスポットを過ぎると辺りの雰囲気は一転。緑は忽然と姿を消し目の前に岩だらけの荒涼とした風景が現れる。「硫黄平」だ。ここは、今も活発な火山活動を続ける山の息吹を感じるエリア。周囲は濃厚な火山ガスが立ちこめ駐停車はもちろん、窓を開けることも禁止されている。“生”と“死”が隣り合うその景色は、目と鼻の先にある「浄土平」の名を一層印象付ける。
[全文を表示]
春の吾妻・雪の回廊・花見処
2018/04/某日
待ち焦がれた目覚めの春へ
全国で続々と夏日を記録した3月。4月に入っても温かい日は続き、東北地方でも例年より10日から1週間程も早い桜の開花宣言となった。異例の暑さに高湯の雪解けも加速するかと思いきやそこは三寒四温、凍て返りの吾妻の春。開通直前の降雪で、磐梯吾妻スカイラインの開通も1週間程遅れたようだ。例年より少々、調子の狂う季節感となった今春。高湯へ春の湯遊びに行くなら、4~5月にかけて訪れたい周辺の花見処を併せてご紹介したい。
磐梯吾妻スカイラインの春の開通を、待ち焦がれた方も多いことだろう。この季節、まだまだ名残の冬が居座る吾妻山は、迫力の雪景が私たちを歓迎してくれる。中でも土湯方面から高湯へ向かう途中、1,622mの最高標高を中心に、鳥子平(とりこだいら)と呼ばれるエリアには、高さ3~4mもの圧巻の雪壁「雪の回廊」が現れる。
いつもなら5月上旬頃まで見られるこの景色も、異例の暑さとなった今春は、開通直後でも2m程だったようだ(写真/高湯観光協会より)。とはいえ、胸のすく絶景スポットのひとつ「天狗の庭」(詳細はこちらのブログを参照)から、眼下に福島盆地を望む天空の大渓谷「つばくろ谷 不動沢橋」へと抜ける道は早春の涼感あふれる、大パノラマが愉しめる。
“山笑う”とはよく言ったものだ。この頃になると、高湯も芽吹いたばかりの細かな緑に覆われ、まさにふわりと、微笑んでいるかのような春の気配に満たされる。壮大にして安らかなその景色は、どこか心癒される懐かしい温かさに充ちている。そんな高湯の春を今回は朝昼夕たっぷり満喫しようと、早速、共同浴場「あったか湯」で夜の貸切風呂の予約したがったが、清掃のため、木曜日は休館。営業時間は朝9時から夜9時まで。私たちのように夜に利用するなら、8時半前までには入館したいところだろう。もちろん、館内には男女別の共同の露天風呂もある(大人250円/中学生以上)。
青空に背中を押され急きょ向かった、近くの「不動滝」(詳細はこちらのブログを参照)は、山桜の花吹雪が迎える美しい世界。雪解けに水かさを増した滝は、生命力あふれる迫力だった。心地よい湿気を帯びた春の森も爽快だが、滝までの散策路は急勾配やぬかるみも多い。訪れる際は、くれぐれも足元に注意していただきたい。
[全文を表示]
冬の贅沢・安達屋、玉子湯、吾妻屋の雪見露天
2018/02/某日
高湯の極上、冬に極まれり
雪月花。古来から日本において風流韻事の景物として愛され、美の基準となっているキーワードだ。今冬、関東や西日本では、数十年に一度という雪の当たり年でもあった。厳寒の2月。県下屈指の豪雪地帯である高湯温泉も、今頃は深い雪に覆われていることだろう。今年も高湯の雪見露天を愉しむ季節の到来だ。
秘湯気分漂う山の鄙湯でありながら、JR福島駅や東北自動車道から車で30~40分と、アクセスに恵まれた高湯温泉は、近年、その人気が高まり、2017年の「温泉総選挙」で見事、環境大臣賞を受賞している。
圧巻の雪景色を愉しみに、いつものワインディングロードを登り辿り着いた温泉街は、思っていたより穏やかだ。お世話になる「安達屋」の方に伺えば、今年の高湯の雪は、さほど酷くはなかったらしい。むしろやや少ないくらいだという。とはいえ、軒先に連なる氷柱の見事さに目を奪われる。
帳場でチェックインの手続きを済ませ、早速、宿自慢の大露天風呂「大気の湯」へ。本来ならじっくりと、湯に浸かりながら待望の雪景色を眺めたいところだが、あいにく夜9時まではご婦人専用タイム。愉しみは食後までとっておくことにした。
私の代わりに薄暮の大露天風呂を愉しんだ連れは、雪明りに浮かぶ詩情たっぷりの世界を堪能したらしく、だいぶ茹で上がった顔で戻ってきた(笑)。
[全文を表示]
高湯と微湯--2つの歴史美湯・静心山荘の秋遊び
2017/10/某日
2つの歴湯に、秋の湯情緒を訪ねて
列島を立て続けに襲った台風が過ぎ去り、空がようやく穏やかさを取り戻した10月下旬。高湯から程近い“微湯(ぬるゆ)温泉”の「旅館 二階堂」が今年7月、国の有形文化財に登録されたという。「玉子湯」の茅葺き湯小屋にも通じるその風情も、ちょうど紅葉の見頃を迎えた頃だろうか。秋の湯情緒を一層引き立てる、由緒あるその2つの歴湯を訪ね、一路高湯へ。
紅葉のベストシーズンらしく、辿り着いた共同浴場「あったか湯」の駐車場は満車状態。列を成す車の誘導に追われる係員の前を、吾妻スカイラインへと向かう車両が次々と追い越していく。
その様子を遠目に見ながら、まずは「玉子湯」へ。本館のフロントで日帰り入浴の手続き(1人700円)を済ませ、ロビーのある4階から湯小屋のある1階へと向かう。敷地内を流れる川沿いに点在する湯小屋と露天風呂棟は、美しく色づいた庭園の中、秋の陽射しにのんびりと佇んでいた。先の台風のせいだろうか、白濁した温泉水が流れる川の水量は、いつもより轟々と賑やかだ。「玉子湯」の風呂は内湯も含め計7つ。とはいえ晴れやかな秋晴れの今日、夫婦や家族、背広姿のサラリーマンまで、日帰りに訪れた温泉客らしき一行は、みな面白いようにこの庭園風呂の奥へ吸い込まれていく(笑)。
透明な空の高さに魅せられ、私たちもまた、開放感満点の露天風呂で五色の世界をどっぷり堪能。やわらかな光を反射し、周囲の彩りに一層映える翡翠色の湯は、短い吾妻の秋を謳歌するような、生き生きとした華やかさに溢れていた。
[全文を表示]
高湯ゆかりの文人編・晩夏の玉子湯にて
2017/08/某日
吾妻の山に故郷を重ねた、斎藤茂吉
立秋を過ぎてまもなく。記録的な長雨に、慌てて毛布を持ち出す程の朝晩の冷え込みが続く(笑)。このぶんだと秋の訪れも早そうだ。これからの季節なら降りしきる雨音を聴きながら、一冊の本を友に夜長を過ごすのもいい。
さて、これまで[開湯伝説](詳細はこちらのブログを参照)・[江戸・明治](詳細はこちらのブログを参照)・[昭和・平成](詳細はこちらのブログを参照)と3回に渡り、高湯の歴史をご紹介してきた。日に日に深まる秋にふさわしく、最後となる今回は高湯ゆかりの文人についてふれてみたい。
良質な温泉と景勝に恵まれた福島県内には、多くの名だたる文人が逗留した。高湯にも斎藤茂吉をはじめ、加藤 楸邨、庄野潤三、埴谷 雄高などの作家が訪れている。歓楽的な温泉地を訪れた泉鏡花や若山牧水、竹久夢二といった文人とは対象的に、高湯を愛した作家は、いずれもどことなく枯淡な雰囲気を宿している。
大正から昭和初期にかけて活躍した歌人、斎藤茂吉(さいとう もきち)は、1913(大正2)年に出版した第一歌集『赤光』の「死にたまふ母」のなかに、吾妻山を詠んでいる。
吾妻やまに雪かがやけば我が母の国に汽車入りにけり
茂吉にとって吾妻は、蔵王と並ぶ故郷の山であった。この歌には、消えかかる母のいのちの灯に、朝日に映える吾妻山を仰ぎ夜汽車で急ぐ茂吉の切なる想いが綴られている。
茂吉が高湯に逗留したのは1916(大正5)年の夏、病床の父の見舞いに山形へ出かけた帰りである。そのときの印象はかなり強かったらしく、茂吉が逗留した「吾妻屋」(詳細はこちらのブログを参照)では宿の主人が「東京の客人庭坂(現:福島市町庭坂・李平)より馬にて来る」と、日記に留めている。そのとき茂吉を高湯に案内したのが信夫郡瀬上町在住の歌人で、生涯の友となる門間春雄(もんま はるお/1889-1919)であった。門馬との出会いは茂吉が編集する「アララギ」で長塚節(ながつか たかし/1879-1915)の追悼号を出版する際、長塚と懇意にしていた門間に原稿を依頼したことに始まる。
五日ふりし雨はるるらし山腹の吾妻のさ霧のぼりみゆ
高湯に滞在中に茂吉が詠んだこの歌は、現在、一切経山と吾妻小富士の間に位置する樋沼(詳しくはこちらのブログを参照)に建立された歌碑にも刻まれている。ちなみに、歌碑建立にあたり吾妻屋で確認された茂吉の歌はもう一首ある。
山の峡(かい)わきいづる湯に人通ふ山ことはにたぎち霊(たま)し湯
吾妻にまつわる歌はこの他にも第二歌集「あらたま」に16首が収録されている。そこには、下界では決して味わえない山での体験に感じ入る茂吉の、瑞々しい日々が推察できる。中にはよほど嬉しかったのだろうか、宿で意気投合した門間を詠んだものもある。
霧こむる吾妻やまはらの硫黄湯に門間春雄とこもりゐにけり
門間はこの来訪からわずか半年後に結核を発病し、30歳という若さで急逝した。門間の歌人としての才能を認めていた茂吉にとって、この衝撃は大きかったようだ。そんな茂吉と門間、高湯温泉の繋がりを記した樋沼の歌碑は2006(平成18)年に経年劣化の修復が行われ、今なお、蔵王と吾妻という二つの故郷に見守られた同じ地で時を刻んでいる。 [全文を表示]
最新記事はこちら
- 名残の冬と美食を愉しむ秘蔵の湯宿、安達屋
- 晩夏に遊ぶ天空の宿、花月ハイランドホテルと信夫山逍遥。
- 緑滴る初夏の癒し湯、ひげの家と浄楽園・中野不動尊。
- 冬ごもりの雪見露天、玉子湯
- 初冬の湯三昧・安達屋、花月ハイランドホテル、玉子湯
- 夏の浄土平湿原・吾妻小富士と静心山荘の寛ぎ
- 春の吾妻・雪の回廊・花見処
- 冬の贅沢・安達屋、玉子湯、吾妻屋の雪見露天
- 高湯と微湯--2つの歴史美湯・静心山荘の秋遊び
- 高湯ゆかりの文人編・晩夏の玉子湯にて
- 高湯 昭和-平成時代編・不動滝と夏露天
- 高湯 江戸-明治時代編・冬の雪見露天巡り
- 高湯はじまり編・晩秋の一切経山を訪ねて
- 吾妻の紅葉巡り・花月ハイランドホテルと浄土平散策②
- 吾妻の紅葉巡り・静心山荘と浄土平散策①
- 晩夏の高湯遊び・安達屋と吾妻小富士
- 秘蔵のぬる湯と創作料理、静心山荘
- 創業140年の山の湯宿「吾妻屋」
- 泉質異なる2つの温泉宿めぐり「のんびり館」
- 大切な人と過ごしたい宿「旅館 ひげの家」